嚥下障害の予防と対策は?有効な治療法を解説
生きていくうえで欠かせない行為であり、日々の楽しみにもなるのが「食事」です。
しかし、老化による筋力低下などさまざまな原因で食事が難しくなってしまう場合があり、その1つが嚥下障害です。
嚥下障害になると、食事をするのがストレスになるため、できるだけ治療などをして筋力低下などを避けたいと思っている人も多いでしょう。
この記事では、嚥下障害の予防と対策、有効な治療法について解説します。
嚥下障害に悩んでいる人、いつまでも食事を楽しみたい人はぜひ最後までご覧ください。
嚥下障害とは?

嚥下障害とは、食べ物をうまく食べられない、飲み物をうまく飲みこめない状態です。
食べ物や飲み物を飲みこんだ際に、飲みこみづらかったり咳き込んでしまったりする経験は誰でもあるでしょう。
たまにであれば問題ありませんが、頻繁におきる場合は嚥下障害かもしれません。
また、嚥下障害は「高齢者がなるもの」といった認識が多いかもしれませんが、嚥下力は50代前後から衰え始めます。
ここでは嚥下障害になる詳しい原因や嚥下障害によっておこる弊害について解説します。
嚥下障害になる原因
嚥下障害になる原因はさまざまですが、主な原因は以下の4つです。
| 原因 | 主な疾患など | 特徴 |
| 器質的原因 | ・口内炎 ・歯周病 ・咽頭炎など | 炎症や腫瘍などによって食べ物の通り道を塞いでしまう |
| 機能的原因 | ・加齢による筋力や反射力の低下 ・脳血管疾患 ・パーキンソン病など | 筋肉や神経に異常があり嚥下がうまくできない |
| 心理的原因 | ・うつ病 ・神経性食欲不振 ・心身症など | 精神疾患により喉の違和感や飲み込みにくさが生じる |
| 薬物的原因 | ・脳機能を抑制する薬物 ・抗精神病薬など | 服用している薬が直接的または間接的に影響している |
どの原因により、嚥下障害になっているかによって最適な治療法が異なります。
また、最近は脳卒中が嚥下障害の最大のリスクであると指摘されています。
中高年になると軽い脳梗塞や脳出血が起こる場合があり、軽度であれば、倒れることはなくても嚥下障害として現れることがあるようです。
「嚥下障害かも?」と思ったらすぐに耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・神経内科・消化器内科・歯科・歯科口腔外科などを受診し、正しい治療を始めましょう。
嚥下障害によって起こる弊害
嚥下障害によって起こる弊害は以下のとおりです。
| 誤嚥性肺炎 | ・食べ物や唾液、細菌などが気道に入り起こる肺炎の一種 ・肺炎のなかでも高齢者に多い死因として有名 ・2022年度日本人の死因6位 |
| 窒息 | ・食べ物や飲み物などが気道を塞いでしまい息ができなくなる状態 ・嚥下する筋力が低下したり咽頭蓋の動きが不十分になったりすると起きやすい |
| 低栄養 | ・食事量が減ったり食事の形が限定されたりすると低栄養状態になりやすい ・低栄養が続けば免疫力・体力・筋力の低下にもつながる ・体力や筋力の低下は生活の質の低下にもつながる |
| 脱水 | ・水分をうまく飲み込めない状態が続くと脱水状態になる ・軽度の脱水で血圧低下によるふらつきや失神が起きる ・重度の脱水が続けば腎臓・肝臓・脳などに重度の損傷が生じる場合も |
| 咽頭残留 | ・嚥下しても咽頭に食べ物などが残ってしまっている状態 ・次の嚥下のタイミングで気道に入って咳き込んでしまう可能性も ・口内環境の悪化で口臭や歯周病などを引き起こす場合も |
| 楽しみの喪失 | ・食事が日々の楽しみになっている場合、食事ができないのは楽しみの喪失につながる ・楽しみの喪失は認知症の悪化やうつ病の発症などにつながる場合も |
嚥下障害の弊害を放置すると命にも関わるため、嚥下障害は放置せず正しい治療を受けるようにしましょう。
嚥下障害の悪化を防ぐ予防と対策
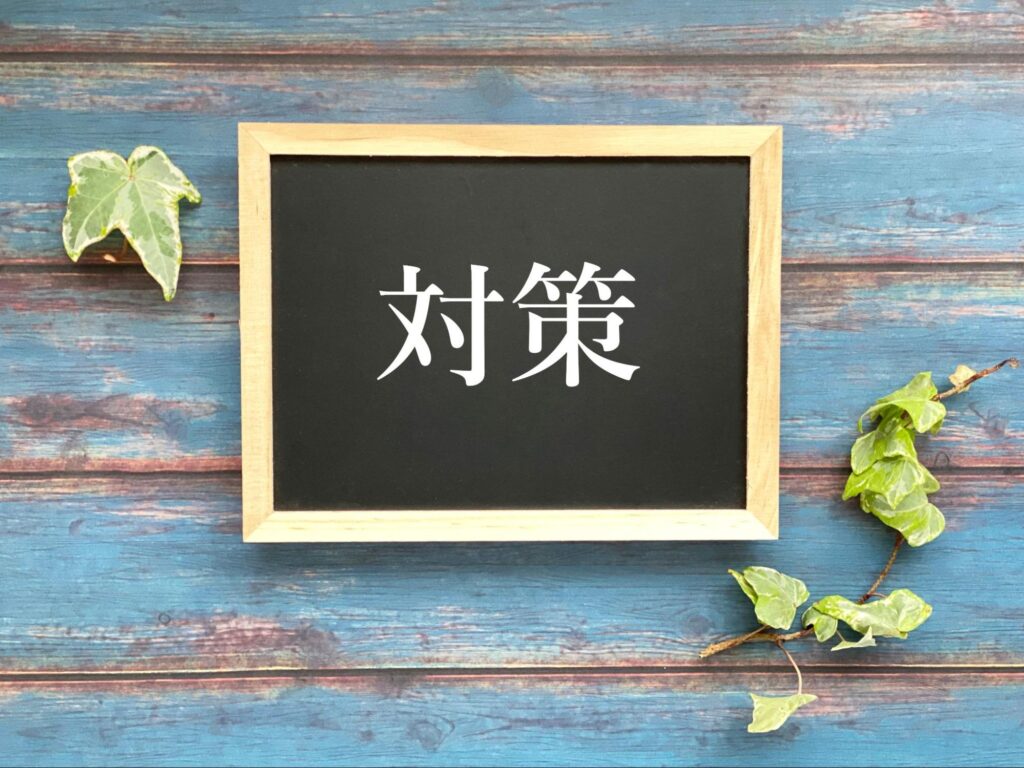
命にもかかわる弊害のある嚥下障害ですが、予防と対策を行うことで嚥下機能の改善などが期待できます。
嚥下障害にならないように予防することも大切ですが、嚥下障害が今以上に悪化しないように対策することも大切です。
ここでは、嚥下障害の悪化を防ぐ予防と対策を3つ解説します。
嚥下レベルにあった食事内容
細かく刻んでいたりとろみがついていたりする食事内容で、介護食や嚥下食と呼ばれる食事があります。
この嚥下食には、食材を煮込んで柔らかく調理したものや、ミキサーなどでペースト状にしたりゼリー状にしたりとさまざまな段階があります。
この段階は長年試行錯誤が重ねられ、病院における臨床研究から作成されました。
| 分類コード | 特徴 | 食品例 |
| コード0j (嚥下訓練食品j) | ・なめらかでべたつかず、まとまりがよく柔らかい離水が少ないゼリー ・噛まずに丸のみできる ・誤嚥した場合を考え、たんぱく質をほぼ含まないものが理想 | ・お茶ゼリー ・果汁ゼリー ・市販の嚥下訓練用ゼリー |
| コード0t (嚥下訓練食品0t) | ・なめらかでべたつかず適度なとろみがありまとまりがある ・噛まなくてもそのまま飲み込めるとろみ状のもの | ・お茶などにとろみをつけたもの |
| コード1j (嚥下調整食1j) | ・なめらかでべたつかず、まとまりがよく柔らかいゼリーやムース状のもの ・たんぱく質が含まれてもよい | ・卵豆腐 ・重湯ゼリー ・ミキサー粥のゼリー ・介護食として市販されているゼリーやムース |
| コード2-1 (嚥下調整食2) | ・ピューレやペースト、ミキサー食など ・まとまりやすいものでスプーンですくって食べる ・咀嚼力は不要だかある程度の嚥下力がある人向け ・コード2のなかでもなめらかな物 | ・粒がなくべたつかないペーストの重湯や粥 |
| コード2-2 (嚥下調整食2) | ・上記内容とほぼ同じ ・コード2のなかでも柔らかい粒などを含むもの | ・粒があり柔らかく離水もなくべたつかない粥 ・温泉卵 |
| コード3 (嚥下調整食3) | ・やわらか食やソフト食 ・舌でつぶせる程度のやわらかさ ・コード2よりも広い範囲の食品を誤飲せずに飲み込める人向け | ・煮込みハンバーグ ・柔らかく仕上げた卵料理 ・固めのゼリー ・粥(三分粥・五分粥・全粥などサラサラではないもの) |
| コード4 (嚥下調整食4) | ・軟菜食や移行食 ・素材や調理法に配慮した食事 ・硬すぎずばらばらになりにくくスプーンやお箸で切れるやわらかさ ・要介護高齢者の食事に近く、誤嚥防止に配慮されている ・嚥下機能や咀嚼力の低下が軽度な人向け | ・軟飯 ・全粥 ・素材に配慮した煮込み料理 ・卵料理 |
コード0が嚥下障害が重い人の食事で、コード4と数字が大きくなる程一般的な食事内容に近づきます。
口や首回りのマッサージやストレッチ
嚥下体操とも呼ばれる、口や首回りのマッサージやストレッチは嚥下に必要な筋肉を刺激し、感覚機能を促すことで嚥下障害の予防や改善、誤嚥のリスク防止につながります。
ここでは自宅でもできる簡単なマッサージやストレッチを紹介します。
- 口をすぼめて深呼吸:鼻から息を吸ってすぼめた口から長く息を吐く
- 首の左右運動:首だけをゆっくりと動かして左右を見るそれぞれ2秒ずつ止める
- 肩の上下運動:首を動かさずに肩だけを上げて1秒、下げて1秒
- 両手を頭の上に組んで体幹を左右に倒す:3秒かけて左に倒し、3秒かけて右に倒す
- 頬を膨らませる:頬を膨らませて3秒、すぼめて3秒
- 舌の出し入れ:1秒で舌を唇よりも前に出し、1秒でひっこめる
- 舌で左右の口角に触れる:舌先が口角に触れるように左右に1秒づつ動かす
- 息を強く吸い込む:喉の奥に空気が当たるように強く息を吸い込む
- 発声:「ぱ・た・か・ら」を1音づつしっかりと発音する
- 口をすぼめて深呼吸:鼻から息を吸ってすぼめた口から長く息を吐く
このような体操は、無理しないようにできる範囲でゆっくり、しっかりと動かすことを意識しましょう。
嚥下運動は食事前に1〜10を1セットとして行ってください。
鏡を見て動きを確認しながら行うのが、より効果的です。
口腔ケアで口のなかを清潔にする
食後の歯磨きやうがい、口腔内の食べ物の残りかすの掃除などの口腔ケアを行いましょう。
口腔ケアは口のなかの清潔を保ち、口臭や虫歯、歯周病の防止ができます。
また、それだけではなく歯や歯肉、口腔粘膜のマッサージを行うことで、機械的な刺激により口腔機能の回復も期待できます。
口腔ケアは食後に家庭でできるものですが、定期的に歯科医院でのケアを受けることでより丁寧で確実なケアが可能です。
当院の訪問歯科についてはコチラのページをご覧ください。
嚥下障害に有効な治療方法

嚥下障害に有効な治療方法は、嚥下障害のレベルや原因などによって異なります。
ここでは2つの嚥下訓練と2つの手術を解説します。
また、嚥下訓練は医療行為に当たるため、必ず医師や歯科医師の指示のもと、行うようにしてください。
食べ物を使用しない「間接訓練」
間接訓練は食べ物を使用せず舌や口のトレーニングを行い、嚥下機能の回復を目指します。
主な訓練内容は以下のとおりです。
- 嚥下諸器官や首・肩周辺の筋肉をほぐし体をリラックスさせるリラクゼーション
- 凍らせた綿棒を水につけて口内を刺激するアイスマッサージ
- 水の入ったコップにストローを使ってぼこぼこと泡を作るブローイング訓練
- 誤嚥した際に咳で食べ物を排出できるように筋力を鍛える呼吸訓練 など
間接訓練は、実際の食べ物を使用した直接訓練を行うと誤嚥などのリスクが高い人や、直接訓練前・食事前の準備運動として行う場合が多いです。
食べ物を使用する「直接訓練」
直接訓練は実際に食べ物を使用して行うトレーニングで、嚥下機能の回復を目指します。
主な訓練内容は以下のとおりです。
- 嚥下レベルに合わせた介護食の提供
- パサついたものを食べたあとにゼリーなどとろみの付いたものを食べる交互嚥下
- 嚥下時に頸部を回し、食べ物が食道側に通過しやすいように誘導する横向き嚥下
- 通常の一口分を複数回に分けて飲み込む複数回嚥下 など
直接訓練は、間接訓練よりも誤嚥や窒息のリスクが高いため、より体調などの細やかな見守りが必要です。
もし、異変があればすぐに訓練を中止して、医師の判断を仰いでください。
誤嚥をなるべく減らす「嚥下機能改善手術」
嚥下機能改善手術は、リハビリや嚥下訓練などを行ったにもかかわらず嚥下機能の回復が見られない場合に誤嚥をできるだけ減らす手術です。
術後にはリハビリや嚥下訓練を再び行い、嚥下機能の回復を狙います。
ただ、術後のリハビリなどでも嚥下機能の回復が見込めないと判断された場合は、次の誤嚥防止術を検討しましょう。
食道と気道を分割する「誤嚥防止術」
誤嚥防止術とは、食道と気道を分離する手術の総称であり、致命的な誤嚥性肺炎を回避する手術です。
確実に誤嚥性肺炎を回避できる手術法ではありますが、食道と気道を分離するため発声機能が失われる可能性があります。
発声機能が失われることは患者と家族への心理的負担が大きく、咽頭を温存するほかの術式が選ばれる場合もあります。
まとめ
この記事では、嚥下障害の予防と対策、有効な治療法について解説しました。
嚥下障害とは、食べ物をうまく食べられない、飲み物をうまく飲みこめない状態です。
嚥下障害になる原因には、器質的原因・機能的原因・心理的原因・薬物的原因があり、命に関わる弊害もあるため、「嚥下障害かも?」と思ったらすぐに病院を受診してください。
『岡崎歯科』では、「すべての人に必要な医療を」の考えのもと、さまざまな患者様が治療を受けられる環境を目指しています。
嚥下障害の悪化や改善が期待できる口腔内ケアをしたいと考えている方は、定期的な歯科医院でのケアも非常に重要です。
また、『岡崎歯科』では通院が難しい人のために訪問歯科も行っています。
歯科医師がご自宅まで訪問させていただくことで、誤嚥性肺炎だけではなく口腔内のさまざまな状況を改善できます。
歯科医院での口腔内のケアや訪問歯科に興味がある方は、ぜひ『岡崎歯科』までお気軽にお問い合わせください。
#訪問歯科 #嚥下 #咀嚼 #咀嚼・嚥下障害 #咀嚼・嚥下訓練
