嚥下時にむせる・咳き込むのはなぜ?その原因と有効な対策を解説
食べ物や飲み物を飲み込む時の一連の流れを「嚥下」と言いますが、一部の方はうまくいかず、嚥下中にむせ込むことや咳き込むことがあります。
このような状態は食事を困難にしてしまい、時には誤嚥や窒息などを引き起こし、健康被害につながる恐れもあるため、周囲の注意や改善が必要です。
嚥下で起こるむせ込みや咳き込みの原因やその対処法などを知っておけば、今までよりも安心して飲食しやすくなるでしょう。
飲食しやすくなって食事が楽しくなり、食べる量が増えれば健康増進効果も期待できます。
この記事では、嚥下時に起こるむせ込みや咳き込みの原因、日頃からできる対策などについて詳しく紹介します。
嚥下時のむせ込み・咳き込みはなぜ起こる?

嚥下時のむせ込みが起こることには原因があります。ここでは嚥下時のむせ込みに関係する身体のメカニズムや、むせ込みの原因などについて紹介します。
嚥下時にむせ込みや咳き込みが起こるメカニズムは?
嚥下時にむせてしまう現象は、身体のメカニズムに関係しています。
食べ物や飲み物が誤って気道に入ろうとすると、身体は反射的に咳をしてそれらを排除しようとします。この反射的な反応が「むせる」「咳き込む」という現象です。
飲食をする際、通常、喉頭蓋(こうとうがい)が気道を閉じることで食べ物や飲み物が誤って気管に入らないようにしますが、この機能がうまく働かない場合にむせたり咳き込んだりすることがあります。
飲食の時だけではなく、日常生活の中で「唾液を飲み込もうとするだけでむせる・咳が出る」という状態が顕著であれば、飲み込むプロセスに問題が発生している可能性があります。
そのような状態は嚥下障害の恐れもあるため、早めに耳鼻咽喉科や消化器科、歯科などを受診してみてください。嚥下障害が起こると以下のような悪影響が出る可能性があります。
- 上手く食べられない・飲み込めない
- 低栄養・脱水症状などになりやすくなる
- 誤嚥のリスクが高まる(誤嚥性肺炎のリスクも高まる)
このような状態は健康を損ね、時として生命の危険も招いてしまいます。
岡崎歯科でも嚥下時のむせや咳き込みなどについてご相談やご受診が可能ですので、お気づきの点があれば早めにご連絡ください。
むせ込み・咳き込みの主な原因
嚥下時のむせ込み・咳き込みの原因はさまざまですが、加齢・神経障害・筋力低下・口腔内や咽頭の異常などが考えられます。それぞれ以下のようなことが要因にあたります。
| 加齢 | 年齢を重ねると嚥下機能が衰えやすくなる |
| 神経障害 | パーキンソン病や脳卒中などの神経疾患 |
| 筋力低下 | 嚥下に必要な筋力が低下している |
| 口腔や咽頭の異常 | 口内炎や咽頭炎などの炎症が起きている |
このような状態はむせ込みや咳き込みを誘発する原因です。
心当たりのある方は医療機関を受診する・日常的にできる対策を取るなどの工夫をして改善を目指してみてください。
嚥下時のむせ込みや咳き込みを防ぐ食事の工夫

通常の食事でむせ込みや咳き込みが起こる場合、食事内容を見直すと改善されるケースがあります。ここでは、むせ込みや咳き込み対策になる食事の工夫について紹介します。
食べ物の形状と硬さ
やわらかくしたもの、ペースト状にしたものは嚥下しにくくなっている人の食事に適しています。例えば以下のようなものがおすすめです。
- 蒸し料理
- 煮込み料理
- ペーストやピューレ状にした果物・野菜
ご本人の嚥下機能の状態によって選択するものは変わりますが、「やわらかい」「飲み込みやすい」を意識するとよいでしょう。
硬いものは飲み込みにくいため、むせ込みや咳き込みが起こりやすいだけではなく、誤嚥や食欲不振、消化不良などにもつながります。
一方、やわらかくしたものやペースト状にしたものは飲み込みやすい上に消化しやすいという利点もあるため、健康増進効果も期待できるでしょう。
とろみをつける
飲食物にとろみをつけ、食べやすさや飲みやすさを向上させるとむせ込みや咳き込みを防ぎやすくなります。とろみをつけることで以下のようなメリットが生まれるためです。
- 食べ物・飲み物が喉をゆっくりと通過し、誤嚥が防げる
- とろみで食べ物・飲み物がまとまり、飲み込みやすい
とろみを付ける際には片栗粉や葛などが役立ちます。最初からゼリー状になっている市販の飲み物もおすすめです。
また、最近は誤嚥防止になる手軽なとろみ剤なども薬局やドラッグストアなどで多数販売されているため、上手に活用していきましょう。
とろみのつけ過ぎには注意を!
前述の通り、食べ物・飲み物にとろみをつけることはむせ込みや咳き込みを防止するために有効な方法です。
しかし、とろみをつけ過ぎると粘度が高くなった液体などが喉に張り付き(咽頭残留物)、誤嚥の原因になることもあります。
とろみをつける時には日本摂食嚥下リハビリテーション学会が推奨する「とろみの3段階」を意識してみてください。
| 薄いとろみ | ・傾けたスプーンからスッと流れ落ちる ・ストローで吸いやすい |
| 中間のとろみ | ・傾けたスプーンからとろとろ流れる ・ストローでは吸いにくい |
| 濃いとろみ | ・傾けたスプーンから流れにくい、形状をある程度保っている ・ストローで吸うのは難しくスプーンの使用を推奨 |
ご本人の嚥下状態によって適したとろみは異なるため、適切なとろみの段階を見つけていきましょう。
ひとくちの量を減らす
ひとくちを小さくしてゆっくりと飲み込むことにより、嚥下のタイミングを合わせやすくなり、むせ込みや咳き込み、誤嚥などを防ぎやすくなります。
一度に大量の食べ物や飲み物を口に入れると、飲み込む際にむせ込みや咳き込みが出るリスクが高まり、非常に危険です。食事の際は「小さなひとくちをゆっくり」と意識してみてください。
また、食事のペースにも余裕を持たせ、飲み込みやすくなるように十分咀嚼することを心掛けましょう。
嚥下訓練を取り入れた対策もおすすめ
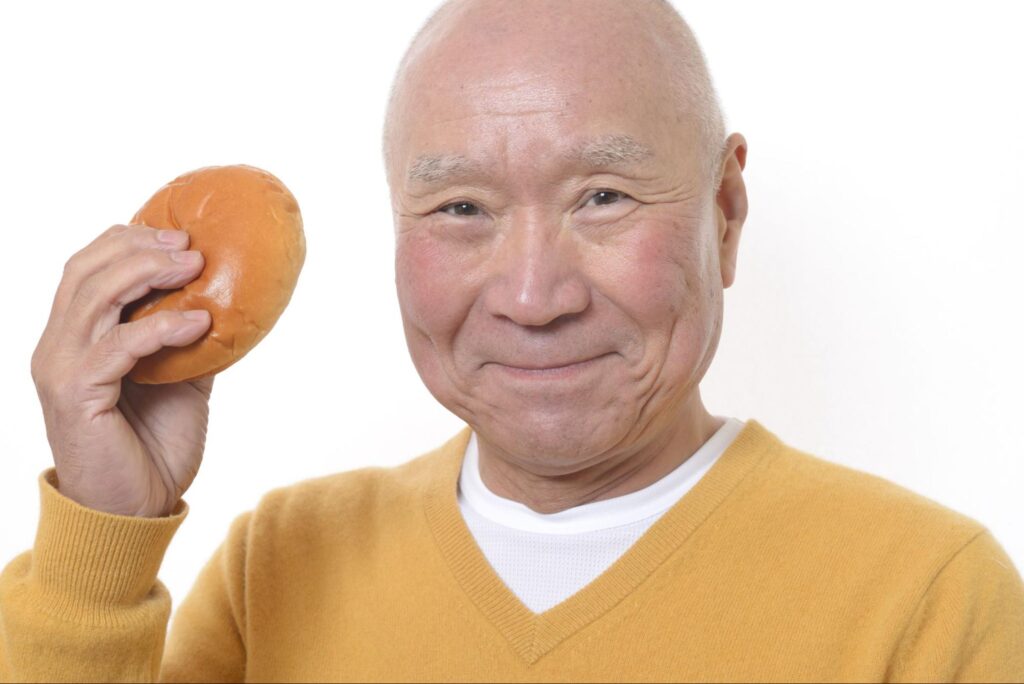
むせ込みや咳き込み対策として、嚥下機能を向上させるための訓練も有効です。嚥下障害の程度に応じて専門家の指導を受けられればなおよいでしょう。
ここでは、むせ込みや咳き込み対策に効果的な嚥下訓練について紹介します。
口腔体操
口腔体操は、嚥下機能を改善するための基本的な訓練です。口の周りの筋肉を鍛えることで、嚥下の力を強化します。具体的には以下のような運動があります。
- 唇をすぼめたり横に広げたりする
- 舌を上下左右に動かす
このような体操を毎日続けることにより、口腔内の筋力が向上し、嚥下がスムーズになるでしょう。
呼吸法の練習
呼吸法の練習も嚥下機能を改善するために重要です。正しい呼吸法を身につけることで、嚥下時の気道の閉鎖がスムーズになります。具体的には以下のような運動を試してみてください。
- 両腕を身体の前で組む
- 両腕を上げながら鼻から息を吸う
- 両腕を下げながら口から息を吐く
腕を動かすことが難しい場合には、以下の方法もおすすめです。
- 鼻から深く息を吸う
- 口をすぼめながら細く長く口から息を吐く
呼吸法の練習は嚥下に役立つだけではなく、肺の機能を向上させるメリットもあります。健康維持の一環としても取り入れてみてはいかがでしょうか。
早めに医療機関のサポートを受けることが大切

嚥下でむせ込みや咳き込みが目立ち、心配になった場合には、医療機関の受診や検査を検討してみてください。ここでは、嚥下に適した医療機関や検査などについて紹介します。
歯科医院で継続的・定期的なケア
口腔内の健康状態は嚥下機能に直結するため、歯科医院での継続的・定期的なケアがおすすめです。歯科医院では主に以下のケアを行います。
- 口腔内のむし歯・歯周病などのケア
- 口腔内クリーニング
- 入れ歯の作製・修理
「歯科が嚥下に関係あるの?」と思うかもしれませんが、実際、歯科と嚥下は深い関係があります。
例えばむし歯や歯周病の細菌は、誤嚥によって肺に落ちることによって誤嚥性肺炎を引き起こす厄介な存在ですが、治療や予防をしておけば細菌の数を減らせるため、発症リスクを低下させられます。
入れ歯の作成・修理も重要です。歯がない状態で食事をすると適切な咀嚼ができず、むせ込みや咳き込みの原因になります。
また、「ゆるい・きつい・破損している」などの状態で入れ歯を使い続けると、やはり適切な咀嚼ができません。
このように、歯科は嚥下に関してさまざまな面から患者さんをサポートします。
耳鼻咽喉科の受診
耳鼻咽喉科の受診は、嚥下障害の診断と治療において非常に重要です。専門医が喉や鼻の状態を詳しく診察し、嚥下障害の具体的な原因を特定します。
その上で患者さんの症状に応じた適切な治療を行い、嚥下機能の改善を目指します。
嚥下障害の診断には内視鏡検査や造影検査などが用いられることがあり、このような検査は効果的なリハビリテーションや治療計画に役立てられます。
また、嚥下障害が起きていないとしても、効果的な改善方法や日常で注意するべき点などのアドバイスも受けられます。
嚥下に異常や不安を感じるようなことがあればぜひ一度受診してみてください。
まとめ
嚥下時のむせ込みや咳き込みは、嚥下機能が低下していると起こりやすい現象です。
放置していると誤嚥性肺炎のリスクが高まったり、上手に食事ができず低栄養や脱水症状につながったりする可能性があるため、異常に気づいた場合には早めの受診がおすすめです。
また、食事や日常生活における機能向上訓練などに気を配ることも有効な方法です。たとえば食べ物はとろみをつけ、ひとくちを小さくすると飲み込みやすくなるでしょう。
口腔体操や呼吸法の練習なども、無理のない範囲でぜひ取り入れてみてください。嚥下機能の向上が期待できます。
岡崎歯科では患者さんの嚥下機能のお悩み対応や、誤嚥性肺炎のリスクを低下させるために有効な口腔内ケアなどにも力を入れています。
嚥下時のむせ込みや咳き込みが気になる方は、お早めに岡崎歯科までご相談ください。
#嚥下 #嚥下障害 #訪問歯科 #むせる
