親知らずの抜歯の痛みはいつまで?なぜ痛いの?対処法や注意点を紹介
親知らずが痛い、歯科医院で抜いたほうが良いと言われたなど、抜歯をする前にどの程度の痛みがあるのか心配になる方は多いです。
この記事では、親知らずの抜歯の痛みの実際のところを、痛む理由やいつまで痛いのか、痛みを軽減する方法や注意点などを通して紹介します。
きちんと歯科医院に相談して、繰り返す親知らずの悪影響にしっかり対策しましょう。
親知らずの抜歯は痛い?

親知らずを抜歯するときは、しっかりと局所麻酔をするため、抜歯そのものについては痛みを感じることはまずありません。
特に敏感な人は、術中の歯を割ったり顎の骨を削ったりする音や振動の不快感を『痛み』と捉える場合があるかもしれませんが、基本的には麻酔が効いています。
実際に親知らずの抜歯で痛みがあるのは抜歯後です。
一番痛いのは麻酔が切れたときですが、何も問題がなければ、術後1~2日程で強い痛みは落ち着きます。
そのあと治癒に近付くにつれ、痛み止めが必要のない程度の鈍痛が続きますが、完全に痛みがなくなるまでは、しばらくかかります。
抜歯の痛みが心配で受診に踏み切れない人は多いですが、問題を抱える親知らずは放置しても改善せず、周囲の歯にも影響を及ぼすなど、症状が徐々に悪化します。
痛み止めをタイミングよく飲む、医師の指示を守るなど、術後のケアがきちんとできていれば、抜歯後の痛みに関して心配しすぎる必要はありません。
親知らずの抜歯後が痛い場合とは

親知らずの抜歯のあとに襲う強い痛みの原因は、抜歯だけでなくその後の経過による場合があります。
親知らずの抜歯後が痛い理由を紹介します。
抜いた直後の痛みは、治そうとしているから
親知らずを抜歯する際、歯茎を切開したりまわりの骨を削ったりするため、炎症の反応が起こります。
炎症とは防御反応のことで、腫れや痛みなどを伴います。
『腫れ』は、破壊された患部を治すために血液やリンパ液など必要な成分が集まってきて蓄積されることで起こります。
ひどい場合は口にあめ玉を入れているような頬に見えるくらい腫れる方もいます。
そして『痛み』は、身体に炎症が起こっていることを脳に伝える大切なサインですが、このサインを抑えたからといって、防御能力が低下するというものではありません。
親知らず抜歯後の麻酔が切れたときが一番痛みが強いのは、抜歯後に感覚があるなかで、一番身体が傷ついているためです。
治癒のために闘っている身体の、当然の反応といえます。
ドライソケット
ドライソケットとは、親知らず抜歯後にできる血餅(けっぺい)がうまく作れず、抜歯して穴(抜歯窩・ばっしか)の部分の顎の骨が露出してしまった状態のことです。
血餅とは、抜歯後の出血が抜歯窩に溜まって塊となった、患部を守るかさぶたのようなものです。
その血餅が、うがいなどなんらかの原因で流れてしまったり、血餅ができなかったりした場合、露出している部分が食べ物などの刺激で強い痛みを覚えます。
通常なら血餅は抜歯当日中にできますが、ドライソケットを発症すると抜歯翌日から症状が現れ、抜歯後のような強い痛みがしばらく続きます。
また、せっかくできた血餅がうがいなどで剥がれ、抜歯後3~4日してからドライソケットになる場合もあります。
何も対応せず放置していると、痛みが徐々に増すだけでなく、骨も炎症を起こしてしまう可能性があります。
抜歯後3日目になっても痛みが改善されない、もしくは日を追うごとに痛みが増す場合は、速やかに歯科医院に相談しましょう。
感染症になった場合
人の口のなかは細菌が沢山存在しているため、親知らず抜歯後に感染症を引き起こすことがあります。
通常の菌であれば免疫力で消滅しますが、感染し炎症が起こると化膿して膿が出たり腫れたりなどの症状が現れます。
ドライソケットになった場合も、患部が露出しているため感染しやすい状態といえます。
膿が出るような感染には抗生物質が処方されますが、その場合の痛みは強いため、一緒に痛み止めも処方されるのが普通です。
医師の指示通り服用し、安静にして数日過ごしていれば大体の場合は治りますが、治りが悪い、痛みが強すぎる場合などは重篤な炎症の場合もあるため、受診が必要です。
親知らずの抜歯の痛みはいつまで?

親知らずは、抜歯の時よりも抜歯後のほうが痛みがありますが、その痛みは何日くらい続くのかを紹介します。
親知らず抜歯後の経過の目安として参考にしてください。
痛みの強さを変えながら経過していく
親知らずを抜いたあとは翌日が痛みのピークで、2日目には痛み止めを飲まなくてもいい程度に落ち着きます。
その後は腫れのピークが3~4日程度続きます。
大体1週間ほどで痛みや腫れは治まっていきますが、2週間程度まで鈍痛が続く場合があります。
このように、何もなければ抜歯後1~2週間ほどで、痛みは治まっていきます。
ドライソケットは2週間以上痛みが続く場合も
ドライソケットになると、2週間から長くて1ヶ月くらいの間、抜歯後の強い痛みが続いてしまう場合があります。
本来なら抜歯後3日もすれば痛み止めがいらない程度まで回復しますが、ドライソケットになると血餅ができずに患部の顎の骨や神経が露出するため、痛みや炎症が起こります。
対処法としては、抗生物質の処方、3~4日おきに歯科医院に通って清掃・消毒してもらう、麻酔をして再度傷をつけて出血させ血餅を作るなどがあります。
あまりの痛みに痛み止めが効かない場合もあるなど、日常生活に支障をきたすため、長引かせないためにも早めに受診して対処してもらいましょう。
親知らずの抜歯の痛みを軽減する方法

親知らずの抜歯後の痛みを、少しでも軽減する方法を紹介します。
痛み止めが効くまでの間や、効きがよくない時など、参考にしてみてください。
麻酔が切れる前に痛み止めを飲む
親知らず抜歯後に一番痛いのは、麻酔が切れたときです。術後3~4時間後に麻酔が切れるため、その前に痛み止めを服用しておきましょう。
痛み止めは飲んでから効果が出るまで30分程かかるため、痛くなってから飲むのではなく、先回りして飲むと痛い思いをせずに済みます。
その後も、例えば8時間置きに飲むような痛み止めの場合、痛みのピークを迎える抜歯翌日までの間は、痛みに関係なく時間を計って飲むのも痛みの軽減につながります。
人によっては処方の量では効きがよくない場合もあるため、追加で飲んでもいいか、処方されたときに確認しておくことをおすすめします。
ガーゼを噛む
痛みの原因は、傷口が開いていることと出血も関係しているため、ガーゼを噛んで傷口を軽く圧迫することで、痛みを軽減できる場合があります。
噛みしめすぎたり、乾燥させてしまったりしないよう注意して噛んでみましょう。
頭を高くする
心臓より少し高めになるように枕を高くするなどすると、痛みが少し楽になる可能性があります。
横になったときに頭の位置が低いと、重力による頭への血流がよくなるため、出血量が増えるなど痛みの原因となります。
即効性はないですが、鼓動を打つような痛みは幾分和らぐかもしれません。
冷やす
歯が痛いときによくやる、冷やすという対処法も効果があります。
しかし、冷やしすぎると血液の循環を妨げてしまい、回復が遅れてしまう場合があります。
冷やすとき直接氷を口に入れるなどはせず、濡れタオルを頬にあてる程度にして、痛みの強い抜歯後24時間までの間だけに留めましょう。
柔らかく刺激の少ないものを食べる
抜歯後は患部に刺激を与えたくないほかに、身体も本調子ではないため、柔らかくて消化のいい、優しい味のものを選んで食べましょう。
抜歯後の食事には以下のようなものが適しています。
- ゼリー・ヨーグルト
- シチュー・スープ
- お茶漬け・雑炊・おかゆ
- うどん
- 親子丼
流動食に近いものから選んで食べるようにし、徐々に元の食事に戻しましょう。
痛みがひどいことを理由に、食事を抜いてはいけません。早く回復できるよう、栄養はきちんと摂ってください。
親知らず抜歯後にしてはいけないこと
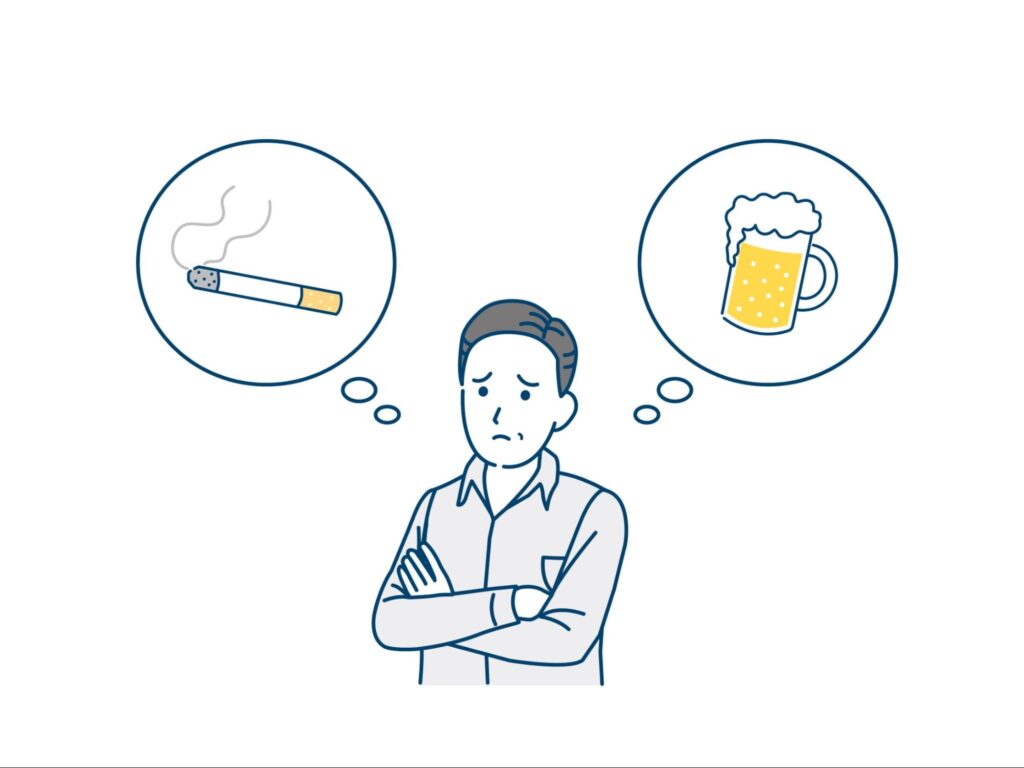
親知らず抜歯後にしてはいけないことを紹介します。
抜歯後の痛みをなるべく長引かせないことにつながるため、ぜひ参考にしてください。
血行がよくなること
基本的に出血を促すような行動は、痛みがひどくなるためおすすめしません。
以下のようなことは、痛みを増すだけでなく、治りも遅くなるため避けましょう。
- 長風呂
- 飲酒
- 激しい運動
お風呂は長風呂でなくても抜歯当日は避け、シャワー程度に抑えておきましょう。
傷に障る物を食べる
親知らず抜歯後はドライソケットの原因にもなるため、刺激の強いものを食べることは避けましょう。
抜歯後の麻酔が効いている間は、間違えて口のなかを噛んでしまう可能性があるため、麻酔が切れてから食べるようにしましょう。
抜歯後当日は柔らかくて刺激の少ないものを、その後は数週間かけて元通りの食事に戻します。
からいもの・固いもの・熱いものなどは、しっかり治癒を待ってから食べましょう。
患部に刺激を与える
以下のようなことで患部に刺激を与えてしまうと、血餅が取れてしまったり、出血や感染の原因となったりします。
- 舌でいじる
- 縫合の糸を引っ張る
- 強いうがい・うがいのしすぎ
- 歯磨き
特にうがいについては、食後などに気になっていても歯ブラシが思うように使えないため、代わりにうがいをする人が多いですが、血餅が取れない程度に留めなければいけません。
細菌が入り込むきっかけにもなってしまうため、気になるようでもなるべく触らないよう気をつけましょう。
喫煙
喫煙をすると血管が収縮して血行が悪くなり、治癒が遅くなるといわれています。
ほかにもタバコの弊害として、傷口が塞がりにくくなったり、免疫力が低下するなどがあります。
特に免疫力が下がると感染するリスクが上がってしまうため、なるべく控えましょう
運転
痛み止めには眠くなるものもあるため、服用中の自動車の運転や、機械の操作等をしないほうがいいでしょう。
どうしても運転をせざるをえない場合などは、眠くならない痛み止めにしてもらえるか相談してみましょう。
体調が万全といえない状態のため、痛み止めを服用していなくても運転には気をつけた方がいいかもしれません。
まとめ
親知らずを抜歯するとなったときに気になる『痛み』について、さまざまな視点から紹介してみましたが、いかがでしたか?
実際の抜歯の際は麻酔が効いていること、抜歯後は痛む前に痛み止めを飲む、感染予防の抗生物質が処方されるなど、紐解いてみれば対策があることが分かって頂けたかと思います。
親知らずの抜歯を決めた歯科医院を信頼し、相談した上で指示に従えば、無駄に痛みを長引かせることにはなりません。
岡崎歯科では、なるべく不安を感じないよう徹底したカウンセリングのもと、一人一人の親知らずと向き合い、最善の治療を提案させていただきます。
その痛みに誰でも躊躇する親知らずの抜歯に安心して踏み切れるよう、岡崎歯科がお手伝いします。
#親知らず #親知らず抜歯痛み
