親知らず抜歯後はいつまで痛い?どう過ごす?症状や経過、注意点を紹介
「親知らず抜いた後って、どんな風になるのかな?」
奥歯を抜くのは誰でも躊躇すると思いますが、斜めに生えたり表に出なかったりするような『親知らず』を抜くとなると、その後のことが心配ですよね。
この記事では、親知らずの抜歯後に現れる症状や、症状の変化・経過、注意点、歯科医に相談が必要なケースなど、詳しく紹介します。
親知らずが引き起こす問題で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
親知らずの抜歯後にみられる症状
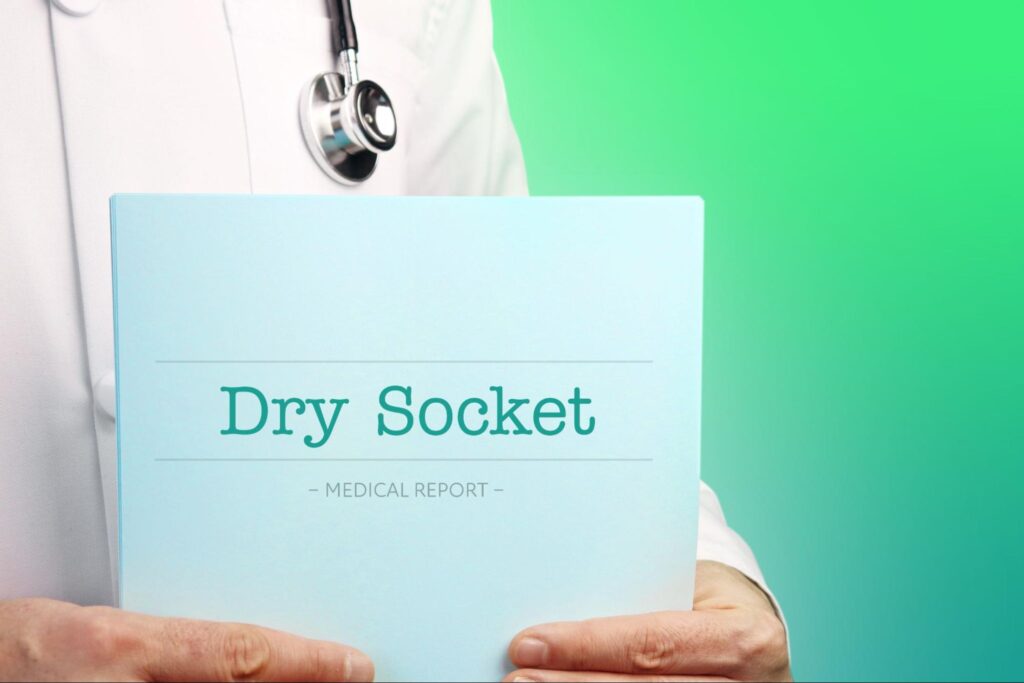
親知らず抜歯後のダウンタイム中は、場合によってさまざまな症状が出ます。
前もって知っていれば対処法を考えておけるため、ぜひ参考にしましょう。
出血
親知らずの抜歯直後は出血するため、ガーゼを15分ほどしっかり噛んで圧迫止血法を行います。
ガーゼを噛む間、抜歯した穴に血の塊ができることで止血しますが、高血圧治療薬などの影響で血が固まりにくくなっている場合など、再び出血したり止血に時間がかかるケースもあります。
15分ほどガーゼを噛んでいても止まらない場合は、ガーゼを取り換えるかティッシュなどを丸めてもう一度15分程度噛んでみます。
1~2日程度の間で、若干血の味がするような程度の出血に治まるのが一般的です。
腫れ
親知らず抜歯後は、当日から抜歯後3日目に向けて腫れていってピークを迎え、その後徐々に腫れが引いていきます。
親知らずを抜歯するとき、生え方次第では歯茎を切開して顎の骨を削る場合があります。
切開した範囲が広かったり、歯を削り取った量が多かったりする場合、腫れやすくなります。
痛み
抜歯後、痛み止めが不要な程度になるには少なくとも1~2日、痛みが完全に引くまではおおよそ1週間から10日ほどかかります。
親知らずの抜歯後から3~4時間ほど経つと麻酔が切れますが、一番痛いのはその麻酔が切れた直後です。
そして痛み止めは飲んでから効き目が現れるまで約30分かかるため、あらかじめ麻酔が効いているうちに指示された量を服用しておくことをおすすめします。
麻酔が切れたあとも、痛み止めを飲む時間の間隔を守りながら、痛む前に服用するのを繰り返すことで、痛みにあまり苦しまずに乗り越えられます。
切開や縫合のある外科的処置をしている場合もあるため、痛みにより口が開きづらくなりますが、1~2週間程度で治まります。
ドライソケット
ドライソケットは、歯を抜いた穴(抜歯窩)に血の塊(血餅)ができず、骨が露出してしまっている状態です。
ドライソケットになると、心臓の鼓動に合わせて脈打つようにズキンズキンとした強い痛みが常にある状態になります。
血餅は抜歯後の出血を抑える、骨の露出を防ぐ、正常な治癒をサポートするなどの役目があります。
うがいのし過ぎや、喫煙による血管収縮作用などによる出血不足が原因で血餅ができない場合があり、その際は消毒や消炎で対応しますが、改善しない場合は再度、外科処置が必要です。
知覚麻痺・知覚過敏
親知らずを抜歯すると知覚麻痺や知覚過敏の症状が現れます。
親知らずの近くには下顎・舌・唇をつなぐ神経があり、抜歯時に少し触れただけで麻痺やしびれが残ることがありますが、長くは続かず1ヶ月くらいで治まります。
痛みが出たり沁みたりする知覚過敏は、抜歯によって歯茎が下がり手前の歯の根が露出することで現れます。2週間~2ヶ月程で治まりますが、予後が悪ければ半年ほどかかります。
発熱
発熱が起こる場合は抜歯翌日から2~3日間程度続き、長くても1週間程度で下がります。
炎症が48時間後のピークを迎えるためですが、麻酔薬が身体に合わない場合や感染・アレルギーを起こしているときにも発熱します。
抜歯後に処方される痛み止めに解熱の成分も含まれているのと、抗生物質も一緒に処方されるのが一般的であるため、麻酔が切れるころにまず痛み止めを服用して様子をみます。
喉の痛み
親知らずの抜歯後、飲食の際の嚥下痛(喉の痛み)が起こることがあります。
特に下顎の親知らずの際に、歯茎を切開したり骨を削ったりして起こる炎症が喉のほうまで広がることで、後遺症として現れます。
抜歯後2~3日が痛みのピークで、約1週間程度で徐々に治まります。
鼻血(上顎洞穿通)
上顎の親知らずの位置は、上顎洞と呼ばれる鼻の横にある副鼻腔に近いため、抜歯をすることで繋がってしまい、出血が鼻に流れ込むことがあります。
抜歯当日に見られる場合と、上顎洞のなかでいったん固まって黒くなった血が1~2週間後に流れ出てくる場合とがあります。
殆どが自然に閉鎖しますが、1ヶ月ほど経っても鼻血が続く場合や、膿が出てくる場合は受診が必要です。
硬直
顎の筋肉が硬直する開口障害が起こり、口を開けにくくなったり、食べ物が噛みづらくなったりすることがあります。
これは正常な反応で、5~10日程度で自然に回復します。
ガムをかむなどして緊張を和らげたり、抗炎症薬であるイブプロフェンを服用したりするのも症状の軽減に有効です。
アザが広がる
内出血のために、顎にアザが広がる場合があります。
皮膚が黒色や青色・緑色・黄色などの色に変化し、首や鎖骨辺りまで広がることがありますが、一過性のものです。
術後2~3日辺りで起こる正常な現象で、2週間頃までに徐々に消えていきます。
骨の突起
抜歯した患部付近で、下に固い突起のようなものが触れる場合があり、歯を取り残したような違和感がありますが、これは抜歯することで空になった部位の、顎の骨の壁です。
突起は回復に向かうにつれて滑らかになっていきますが、患部の状態によって、改善まで少し時間がかかる場合があります。
改善がみられない場合は執刀医が削って滑らかにしてくれます。
上の歯と下の歯の違い
親知らずは上下どちらにも生える可能性がある歯で、どちらの親知らずを抜くのにも痛みはありますが、上下で様子が少し違います。
一般的に上顎は骨が柔らかいため抜歯が比較的簡単で、痛みも軽度といわれています。
一方下顎は骨が固く、親知らずの生える状況や形状が悪いと抜歯もむずかしくなり、時間がかかります。
そうなると比例するように治癒にも時間がかかるため、その分痛みも長く続きます。
しかし歯の状態は人それぞれで、一概に皆同様とはいえないため、一般的な説を鵜呑みにせず、まずは担当医師としっかり相談しましょう。
親知らずの抜歯後の経過

親知らず抜歯後の、治癒の経過を紹介します。
しっかり治していくための大切な過程です。医師の指示を守りながら丁寧に養生するための参考にしてください。
1.歯科医で処方された痛み止め・抗生物質を服用する
親知らずの抜歯後は歯科医院で痛み止めと抗生物質を処方されるため、指示通り服用します。
痛み止めは効果を発揮するまでに時間がかかるため、最初の服用は麻酔が切れる前がおすすめです。
抗生物質は合併症のリスクを避けるための重要な薬です。処方された全てを医師の指示通りにしっかりと飲み終えましょう。
2.当日のうちに血餅(けっぺい)ができる
親知らずの抜歯後の歯茎は、顎の骨が露出しますが、当日のうちに出血は止まり、血餅と呼ばれる血の塊ができます。
かさぶたのような役割を果たす血餅は、治癒まで傷口を守ります。
強くうがいをしたり、頻繁にうがいをすると血餅は形成されづらく、傷の治りも遅くなるため、うがいは控えめにしましょう。
3.食事は抜歯後2~3時間後から
親知らず抜歯後の食事は、麻酔が完全に切れてからにしましょう。麻酔が切れるのは大体2~3時間後くらいです。
麻酔が効いている状態で食事を摂ると、普段噛まない場所を噛んでしまったり、傷口をさらに傷付けてしまったりするためです。
当日はあまり噛まなくてもいいシチューやおかゆ、ゼリーやヨーグルトなどの流動食がおすすめです。
辛いものや熱いものなど、刺激の強いものも避けるようにし、抜歯後3日目以降に様子をみながら通常の食事に戻しますが、抜歯した歯とは反対の歯での咀嚼を徹底しましょう。
4.当日~2日目
痛み止めを用いながら麻酔が切れるときに迎える痛みのピークを凌いでいくと、大体2日目までに徐々に痛みが治まっていきます。
唾液に血の味が混ざることがありますが、感染などの問題が特になければ、痛みに関してはこの辺りで一安心できます。
4.3~4日目:上皮化(歯茎の再生)が始まる
親知らず抜歯後3~4日辺りから、傷ついた歯茎が再生を始めます。
抜いた歯や削った顎は元に戻ることはありませんが、歯茎はしっかりと再生します。
5.1週間後:血餅が肉芽組織に変化
親知らず抜歯後1週間程度経過すると、血餅のなかに血管が入り込んで、肉芽組織に変化します。
肉芽組織とは、損傷を受けて死んだ細胞を食べながら損傷部分を再生していく、増殖力が高い結合組織のことで、ここまで進むと血餅はうがい程度で剥がれることはなくなります。
肉芽組織に変化しなかった血餅はかさぶたのように自然に剥がれ落ち、その後は骨が露出する心配もありません。
抜歯後1週間のこの辺りまでは安静が必要です。
6.10日目:抜糸
親知らず抜歯後10日ほど経つと、切開し縫合した糸を抜糸します。
使った糸の素材や太さ、結び目の強さなどで違いはありますが、抜糸の際の痛みは基本的に殆どないといわれています。
7.3週間~1ヶ月ほどで傷口がふさがり始める
個人差はそれぞれありますが、親知らず抜歯後3週間~1ヶ月ほど経つと、歯茎が傷口を覆います。
まだ、抜歯によって開いた穴がしっかり埋まったり、骨が治ったりする段階ではないため、へこみが残っています。
あまり固いものを噛むなどの無理をしてはいけない時期です。
8.6ヶ月~1年で、抜歯後の穴(抜歯窩)が治癒する
親知らず抜歯後6ヶ月~1年ほどかけて、やっと歯茎や骨が完成し、穴がしっかり埋まります。
抜歯した際に空いた穴を『抜歯窩(ばっしか)』といいますが、レントゲンを撮ってもその痕が分からないくらいの回復が可能です。
親知らず抜歯後の注意点

親知らず抜歯後に気をつけて欲しいポイントを紹介します。
抜歯後のつらい症状を少しでも楽に過ごすために、ぜひ参考にしてください。
抜歯後数日は安静に過ごす
親知らず抜歯後の3日~1週間程度はできるだけ安静にして過ごしましょう。
抜歯後、傷口を守る血餅ができるまでは出血しやすくなっています。
激しい運動やいつも通りの長時間の入浴・アルコールの接種など、血行がよくなったり体温が上がるようなことは避けましょう。
強いうがいをしない
親知らず抜歯後の24時間程度は、血餅が早くできるようになるべく強いうがいをしないようにしましょう。
出血を気にしてうがいをしすぎると、せっかくできた血餅が剥がれてドライソケットにつながります。
食後などどうしても気になる場合は、水を口に含んで吐きだす程度にしましょう。
患部を触らない
抜歯したあとはどうしても患部が気になりますが、できるだけ舌や指・食べたものなどで触らないようにしましょう。
違和感があるため舌先で刺激しがちですが、せっかくできた血餅を剥がしてしまうと治癒が遅くなり、細菌に感染するリスクも上がります。
同じ理由で、歯ブラシも刺激が強いため使うのは避け、抜歯後2~3日は待ってから、軽くブラシを当てる程度に留めておきましょう。
縫合の糸をいじらない
歯茎を切開して縫合した場合、縫合の糸に違和感がありますが、引っ張ったり取ったりすることのないようにしましょう。
抜糸は親知らず抜歯後、順調であれば約1週間ほどで行われるため、それまではできるだけ縫合の糸を刺激するなど負担をかけないようにします。
薬は指示を守って服用する
親知らずの抜歯後は感染予防のために抗生物質が処方されますが、医師の指示通り服用し、飲み忘れたりかってに中断したりしてはいけません。
痛み止めも、決められた時間間隔をしっかり空けて、いくら痛くても飲みすぎないよう気をつけましょう。
抗生物質は、一日の服用回数や飲む時間など、それぞれの決まった飲み方を守ることで、血液内の薬の濃度を一定に保つ必要があります。
ただでさえ口のなかは細菌でいっぱいです。感染によって食事が摂れなくなって体力が落ちることなどを考えると、抗生物質を指示通り服用して感染予防することはとても大切です。
タバコを吸わない
親知らず抜歯後は、普段毎日タバコを吸っている人も、2~3日は喫煙を控えるようにしましょう。
タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させて血流を悪くする働きがあります。
すると血液が不足した状態になり、傷の治りを遅くし、血餅が作られにくくなり、感染症のリスクが高まり、薬が効きにくくなります。
痛みが長引くドライソケットも引き起こすタバコは、2~3日といわずできれば完治するまで吸わないことをおすすめします。
歯科の受診が必要なケース
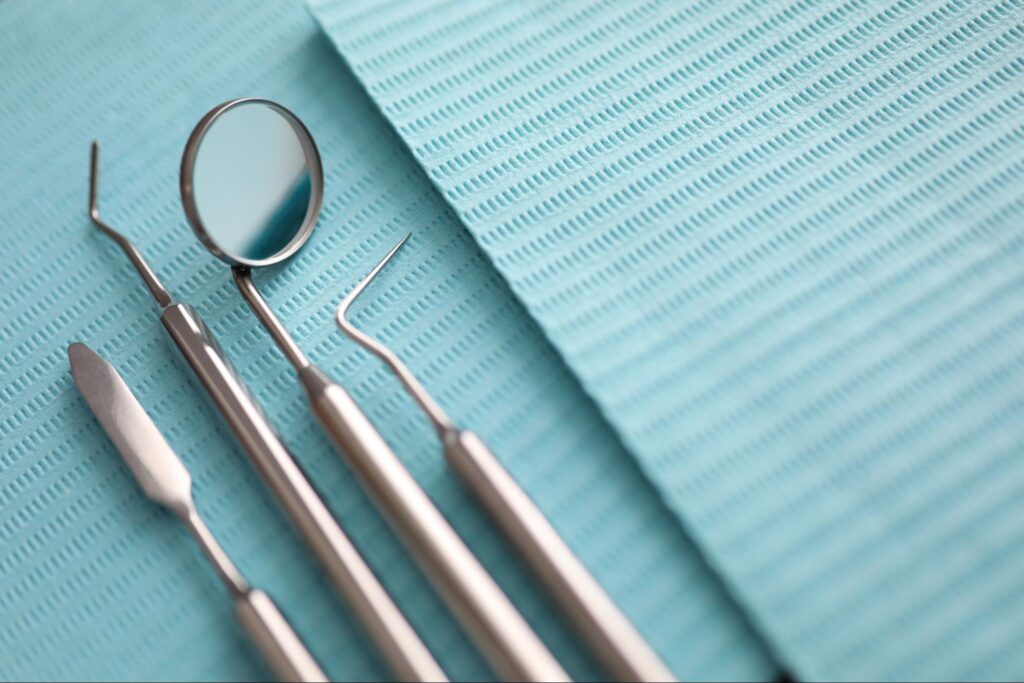
親知らず抜歯後の症状で、受診が必要なケースを紹介します。
以下のような症状がある場合は、抜歯した歯科医院をなるべく早く受診するようにしましょう。
2~3日を過ぎても体温が高め・発熱している
親知らず抜歯後は、抜歯翌日から2~3日は38℃程度の発熱がある場合があります。
たまたま体調の悪いときに抜歯していたり、抜き方に問題があったりと、抜歯後に問題があるわけではないことも考えられます。
処方された抗生物質をきちんと服用して安静にしていれば治まることが殆どですが、それ以上続くようであれば、抜歯を行った歯科医院を受診しましょう。
3日目を過ぎてから腫れが強くなった
親知らずの抜歯で腫れる場合は通常、抜歯後2~3日がピークで、長くても1週間程度で引きます。
それを過ぎても腫れや痛みが引かない、腫れが大きくなる場合は状態が悪化しています。
考えられるのは感染か、何かを取り残しているケースで、放置すると炎症が進んでしまうため、早々に抜歯をした歯科医院を受診しましょう。
4日目を過ぎて痛みが強くなった
通常は親知らず抜歯後4日目になると、がまんできる鈍痛へと変わり、1週間もする頃には(2週間ほどかかる場合もありますが)痛みは殆どない状態になります。
もし4日目を過ぎても強い痛みが続く場合、抜歯した歯茎の穴がドライソケットになっているかもしれません。
その場合、放置していても1ヶ月もすれば自然に治りますが、その間痛みが続くため、早いうちに歯科医院を受診し、痛み止めと抗生物質を処方してもらいましょう。
出血が多すぎる
親知らずを抜歯した場合、翌日の午前中辺りまでの滲む程度の出血については心配ありませんが、流れるように出血する場合、早々に止血しなければいけません。
清潔なガーゼやティッシュを穴より少し大きめに固く丸めて、圧迫するように噛んで20分程度待ちます。その間、何度も外して様子を見るのはやめましょう。
上記を2~3回繰り返してみて、最終的に血が滲む程度になったら噛んでいるものを外して様子を見ます。
それでもドクドクと血が流れるようであれば夜間でも受診してください。
血が止まらないといってうがいをすると余計止まりにくくなるため控えましょう。
薬の服用後の様子がおかしい
薬との相性が悪かったりアレルギーがあったりすると、湿疹やかゆみ、腹痛や下痢など、予期せぬ症状が引き起こされる場合があります。
薬の副作用としてのものや、指示と違う飲み方をした場合などが考えられます。
日常的に服用している薬がある場合、飲み合わせを考える必要があるため、術前の受診時にお薬手帳などを見せておくことで、処方時に対処してもらえます。
人によっては気分が悪くなるなど、必ずしも一般的な副作用ではない場合もあるため、気になる場合は遠慮せず医師に相談しましょう。
まとめ
親知らずの抜歯後について、現れる症状や治癒までの経過、注意点や受診が必要なケースなどを紹介しました。
外科的手術となるため恐いイメージですが、度々問題を起こす親知らずを放置するリスクはもっと恐い事態につながりかねません。
口のなかは痛みに敏感であることを踏まえ、なるべく苦痛のないように処置できるよう、岡崎歯科でも日々研鑽を重ねています。
親知らずの抜歯についての不安を、お気軽に岡崎歯科にお聞かせください。しっかりと相談したうえで、一緒に解決しましょう。
#親知らず #親知らず抜歯後
