高齢者の摂食・嚥下機能の変化とは?主な症状や機能を低下させない方法を紹介
摂食・嚥下機能低下の原因は体の病気や心因性疾患などさまざまですが、高齢者の場合は加齢による機能低下も原因の1つです。
高齢者の摂食・嚥下機能はどのように変化していくのでしょうか。
また、摂食・嚥下機能を低下させないための対策などを知っておくことで、楽しみながら食べ続けられます。
この記事では、高齢者の摂食・嚥下機能の変化や主な症状、機能低下させない方法などを紹介します。
いつまでも食事を楽しみたい人、摂食・嚥下機能低下を防ぎたい人はぜひ最後までご覧ください。
高齢者の摂食・嚥下機能の変化

高齢になると、体のさまざまな機能に衰えや変化が生じます。
私達が毎日意識せず行っている「摂食(食べる)」という行為は複雑な仕組みで成り立っており、加齢によって何らかの障害や機能低下が起こると、摂食・嚥下障害につながってしまうことがあります。
高齢者の摂食・嚥下機能に影響を及ぼすのは、主に以下のような変化です。
- 嚥下に関する筋力や反射力の低下
- 唾液分泌量の低下
- 歯の喪失(虫歯や歯周病など)
- 味覚低下・口腔感覚の鈍化
- 薬物や疾患
ここでは、高齢者の摂食・嚥下機能の変化についてそれぞれ詳しく解説します。
摂食・嚥下に関する筋力や反射力の低下
摂食・嚥下は口内や喉元などさまざまな筋肉や反射を使用して一連の動きを行っています。
筋力の低下は咽頭の閉鎖などが不十分になり誤嚥を引き起こす可能性があります。
嚥下後口内に食べ物などが残ってしまうこともあり、残った食べかすに細菌などが繁殖し、口内が不衛生になって虫歯や歯周病につながるかもしれません。
また、摂食・嚥下行為は咀嚼など意識的に行える部分もありますが、咽頭から食道へ運ぶ段階などは意識的におこなえない反射部分です。
咽頭から食道へ運ぶ段階は約0.5秒以内の短時間で行われますが、反射力が低下することで誤嚥などにつながります。
唾液分泌量の低下
高齢になると、咀嚼力の低下や唾液腺の萎縮などが原因で唾液の分泌量が低下します。
唾液の役割は以下のとおりです。
- 咀嚼時に分泌され食べ物と混ざることで消化を助ける
- 食べ物を柔らかくまとめて嚥下しやすい形にする
- 細菌の繁殖を防ぐ
- 口内の汚れを洗い流す など
唾液分泌量の低下はこれらすべてに影響を与えます。
唾液分泌量が低下し、口内が乾燥すると食事が取りにくくなり、摂食・嚥下障害につながるだけではなく口内環境の悪化のリスクが高くなります。
歯の喪失(虫歯や歯周病など)
摂食・嚥下に関する筋力や唾液分泌量の低下は口内環境の悪化につながり、虫歯や歯周病などによる歯の喪失につながる可能性が高いです。
また、歯の喪失で本数が減ることでも摂食・嚥下に関する筋力につながるため、摂食・嚥下障害の悪循環に陥ります。
歯の喪失は健康寿命にも大きなかかわりがあり、歯の喪失が10歯以上になると食生活などに大きな影響が出るといわれています。
味覚低下・口腔感覚の鈍化
味を感じる味蕾の減少による味覚低下や口内感覚の鈍化などは加齢によって誰にでも生じるものであり、避けられない部分でもあります。
味覚低下は食事に対する意欲や興味低下につながり、口腔感覚の鈍化は咽頭などに食べ物が残りやすくなり口内環境の悪化や誤嚥につながります。
薬物や疾患
薬物や疾患も摂食・嚥下機能に影響します。
高齢者になると免疫力の低下などが原因でいくつかの疾患を併発していたり、それに伴い薬を服用したりすることが多いです。
疾患のなかでも、脳梗塞や脳卒中などの脳血管疾患は、脳にダメージを与えるため咀嚼や嚥下をする際の神経や器官を動かすための指令がスムーズに届かなくなる場合があります。
また、服用している薬の効果や副作用によっては、咀嚼・嚥下機能の低下を招くことがあります。
例えば、脳機能を抑制する薬や唾液分泌量が減少する副作用がある抗ヒスタミン剤などです。
摂食・嚥下障害の主な症状
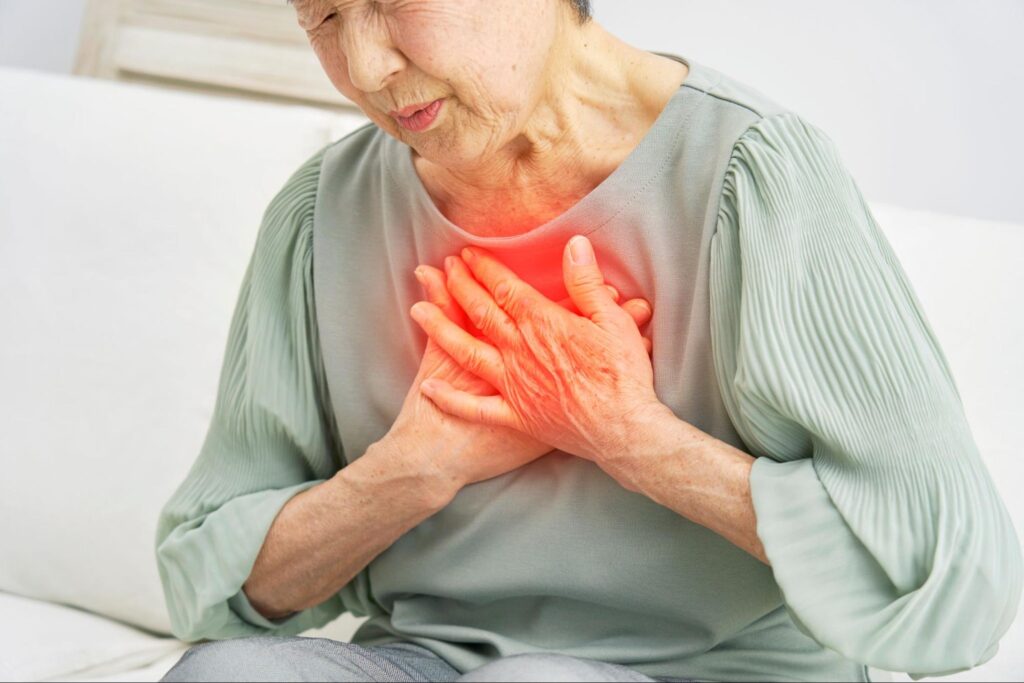
摂食・嚥下障害の主な症状は以下の8つです。
- 食べ物が飲み込みにくくなったと自覚がある(嚥下困難)
- 食事や飲み物を飲む時にむせる(誤嚥)
- 食事に時間がかかる
- 食事で疲れる
- 食べ物が口からこぼれる
- 飲み込んだあとも口のなかに食べ物が残っている(咽頭残留)
- 食事中や食事後に咳や痰が出る
- 食事後に声が変わる など
このような症状は摂食・嚥下する際のどの部分に不具合があるのか、どのような原因で不具合が起きているのかによって、強く出る症状が異なる場合があります。
加齢が原因となっている場合は急激な変化が少なく症状に気づきにくいことがあり、気付いた頃には悪化してしまっているケースもあります。
毎日の食事風景で、少しでも違和感や異変があればすぐに医療機関を受診しましょう。
摂食・嚥下機能の低下を予防する方法

高齢者が摂食・嚥下機能を低下させないための方法はいくつかあります。
ここでは、摂食・嚥下機能を低下させたくない人に、ぜひ実践してほしい3つの方法を解説します。
筋力の維持
高齢者が摂食・嚥下機能低下する原因の1つで多いのが筋力の低下です。
筋力の低下を阻止・維持するためには、口をすぼめたり舌をだす嚥下体操の実施が効果的です。
日常的に簡単にできる嚥下体操を紹介します。
- 口をすぼめて深呼吸:鼻から息を吸ってすぼめた口から長く息を吐く
- 首の左右運動:首だけをゆっくりと動かして左右を見るそれぞれ2秒ずつ止める
- 肩の上下運動:首を動かさずに肩だけを上げて1秒、下げて1秒
- 両手を頭の上に組んで体幹を左右に倒す:3秒かけて左に倒し、3秒かけて右に倒す
- 頬を膨らませる:頬を膨らませて3秒、すぼめて3秒
- 舌の出し入れ:1秒で舌を唇よりも前に出し、1秒でひっこめる
- 舌で左右の口角に触れる:舌先が口角に触れるように左右に1秒ずつ動かす
- 息を強く吸い込む:喉の奥に空気が当たるように強く息を吸い込む
- 発声:「ぱ・た・か・ら」を1音ずつしっかりと発音する
- 口をすぼめて深呼吸:鼻から息を吸ってすぼめた口から長く息を吐く
摂食・嚥下に使用する筋肉だけではなく、身体を動かして全身の筋力維持を目指すことも効果があるといわれています。
筋力維持のための運動や体操をする際には、決して無理をせず自分のできる範囲で行うようにしてください。
適切な口腔ケア
食後の歯磨きや入れ歯の手入れなど適切な口腔ケアを行い、口内の清潔を保つことも大切です。
口内や歯を清潔に保つことで、虫歯や歯周病の予防になり咀嚼機能の低下を防ぎます。
また、口腔内を刺激すると唾液の分泌を活性化させることができ、咀嚼時に食べ物を柔らかくしてくれるため嚥下しやすい状態になります。
日常的な口腔ケアは歯磨き・うがいや入れ歯の手入れ、舌磨きなどがありますが、定期的に歯科医を受診し、口内の状態を正しく確認しておきましょう。
岡崎歯科では、実際に当院に来て受診頂くこともできますが、訪問歯科についても対応しています。
当院の訪問歯科についてはコチラのページをご覧ください。
食事中は食事に集中
食事中は食事に集中できるようにテレビなどを消し、意識がほかに向かないようにしましょう。
意識が食事以外に移ってしまう環境では、口の動きが止まってしまいむせる原因になります。
また、食事が終わったあとにすぐに横になるのも避けてください。
食後すぐに横になると食べ物が逆流し、嘔吐や誤嚥につながる可能性があります。
医療機関で行われる摂食・嚥下機能維持のためのリハビリ

摂食・嚥下機能維持や低下してしまった際の改善に効果的なのがリハビリです。
ここでは、医療機関で行われる摂食・嚥下機能維持のためのリハビリについて紹介します。
リハビリは継続的に行う必要がある
摂食・嚥下機能維持のためのリハビリは、継続的に行う必要があります。
リハビリによって摂食・嚥下機能が一時的に回復したとしても、放置するとまた筋力低下を招く可能性があるためです。
定期的な通院が難しい場合は、訪問診療でのリハビリを利用するといいでしょう。
食べ物を使用しない間接訓練
食べ物を使用しない間接訓練では舌や口のトレーニングを主におこない、摂食・嚥下機能の回復を目指します。
主な間接訓練の内容は以下のとおりです。
| 訓練方法 | 内容 |
| リラクゼーション | ・嚥下諸器官や首・肩周辺の筋肉をほぐし体をリラックスさせる ・腕を左右に広げたり深呼吸したりでも効果的 |
| 嚥下体操 | ・直接訓練や食事前に行う準備運動 ・頸部・口唇・舌・頬を中心として動かす ・頸部周辺のストレッチや早口言葉も有効 |
| 感覚向上訓練 | ・アイスマッサージを行う(凍らせた綿棒を水につけて口内を刺激する) ・食べ物を嚥下する際の嚥下反射の誘発を促す |
| ブローイング訓練 | ・水の入ったコップにストローを使ってぼこぼこと泡を作る ・強く吹いたり弱く吹いたり、ストローの太さを変えることで筋力低下を防ぐ |
| 嚥下反射促通手技 | ・アゴから下の筋肉をマッサージして刺激する ・食べ物が口内に残ってうまく嚥下できない際にも行う場合がある |
| 呼吸訓練 | ・誤嚥した際に咳で食べ物を排出できるように筋力を鍛える ・腹式呼吸を意識することで呼吸機能を高める |
| 発声訓練 | ・嚥下するときと同じ器官を使用する「ぱ・た・か・ら」の4音を発声する ・筋力アップや舌の動きをスムーズに行う練習 |
間接訓練は、誤嚥などのリスクがあり直接訓練が難しい人や直接訓練前・食事前の準備運動として行います。
食べ物を使用する直接訓練
直接訓練は実際に食べ物を使用して行うトレーニングで、嚥下機能の回復を目指します。
主な直接訓練の内容は以下のとおりです。
| 訓練方法 | 内容 |
| 食事の調節 | ・嚥下レベルに合わせた食事の提供 ・ゼリー食などから始めて少しずつ通常の食事に移行 |
| 交互嚥下 | ・パサついたものを食べたあとにゼリーなどとろみの付いたものを食べる ・形状の異なる食事を交互に摂取することで食べ物が口腔内に残りにくくなる |
| 複数回嚥下 | ・通常の一口分を複数回に分けて飲み込む ・複数回に分けることで食べ物が口内に残ることを防ぐ |
| スライス型ゼリー丸呑み法 | ・食べ物をうまく食べられない、喉の食べ物カスが残る、しばらく口からの食事をしていなかった人が対象 ・誤嚥防止などの目的がある ・薄くスライスしたゼリーを噛まずに丸のみする |
| 横向き嚥下 | ・嚥下時に頸部を旋回し、食べ物が通過しやすい咽頭側に誘導する ・嚥下前に行うとよりよい |
直接訓練は、間接訓練よりも誤嚥や窒息のリスクが高いため、しっかりと対策した上で行われます。
訪問歯科で嚥下機能のリハビリが受けられます
間接訓練や直接訓練などの摂食・嚥下訓練は、誤嚥や窒息の危険性をともなう行為であるため、医療行為に分類されています。
自己判断で実施するのは危険なため、必ず医師や歯科医師への相談が必要です。
摂食・嚥下機能維持のためにリハビリや口腔内ケアをしたいと考えている方は、訪問歯科も行っている『岡崎歯科』へご相談ください。
歯科医院に通院するのが難しい方でも、歯科医師がご自宅まで訪問させていただくことで、口腔内のさまざまな状況を改善できます。
歯科医院での口腔内のケアやリハビリ、訪問歯科に興味がある方は、ぜひ『岡崎歯科』までお気軽にお問い合わせください。
まとめ
この記事では、高齢者の摂食・嚥下機能の変化や主な症状、機能低下させない方法などを紹介しました。
高齢者の摂食・嚥下機能の変化は加齢が影響する原因と薬物や疾患が原因の場合があります。
高齢者が摂食・嚥下機能を低下させないためには、筋力維持や適切な口腔ケアを行うなどがあります。
医療機関では間接訓練や直接訓練といったリハビリも受けられ、効果的な対策が可能です。
『岡崎歯科』でも摂食・嚥下機能についてのご相談や訪問歯科を実施しておりますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
#摂食・嚥下 #摂食嚥下障害 #訪問歯科
